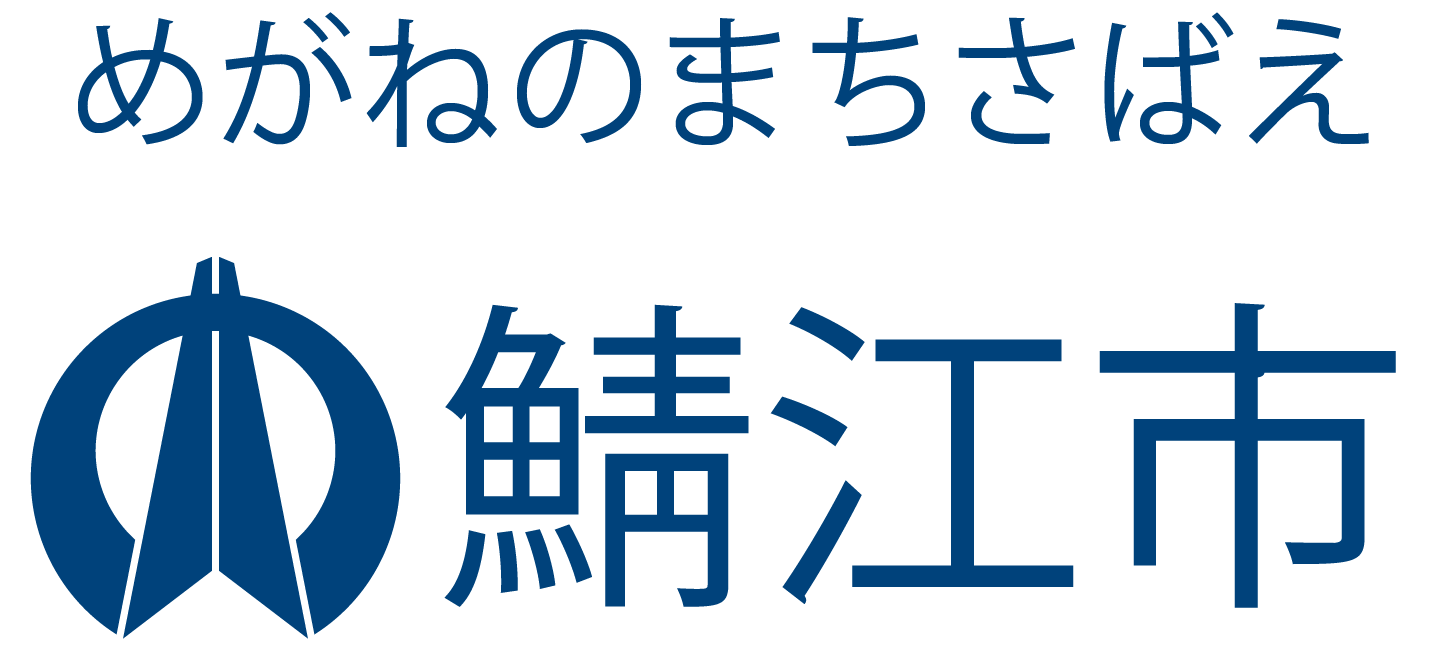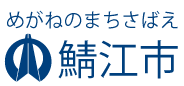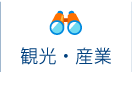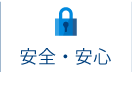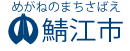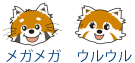西山公園遺跡出土有鉤銅釧
ページ番号:506-508-693
最終更新日:2019年12月25日

指定情報
| 指定 | 《市指定 第58号》 平成10年11月2日 |
|---|---|
| 所在地 | 鯖江市まなべの館 |
| 管理者 | 鯖江市 |
| 時代 | 弥生時代後期前葉~中葉 |
| 員数 | 1点 |
概要
有鉤銅釧は、弥生時代中期に九州北部地域を中心に使用されていたゴホウラ製貝輪を原形として、青銅で鋳造したものである。北部九州を中心に分布し、近畿・東海・関東でも出土しているものの、その数は少なく、これまでに全国で51点しか出土例がない。
この資料は、昭和31年(1956)、西山公園東側中腹(標高約25.6m)において、桜への施肥作業中に地表下30cmから発見されたものである。出土したのは全部で9点(完形品6点、折損品3点)で、8点が東京国立博物館へ、残り1点が鯖江市に寄贈された。全体に偏円形を呈し、一方の長辺に突起(鉤)を持っている。本体部分は長径9.6cm、短径6.4cm(鉤部分を除く)、厚さ0.8cmである。鉤部分は1.4cm外方に突出している。
西山公園遺跡出土有鉤銅釧は、九州北部地域を除けば日本海側では唯一の出土例で、全体の平面形態など、原形となった貝輪の特徴を比較的残している。その用途については不明な部分が多いが、何らかの祭祀の一環として埋納されたか、墳墓の副葬品の可能性が高い。いずれにせよ、当時の長泉寺丘陵周辺にこの稀少な青銅器を入手できる有力集落(あるいはその連合体)が存在したことを示しており、弥生時代後期の鯖江地域の歴史解明のために不可欠の資料といえる。
コラム 青銅器
青銅(ブロンズ)とは銅と錫と鉛の合金である。弥生時代以降、日本でも銅鐸・銅鏡など多数の青銅器が造られたが、鉱石を採掘したり精練した遺跡が未発見であることから、原料を中国から輸入し、日本で鋳造したと考えられている。
※常設展示中です(令和元年12月現在)
本ページの無断転用・転載を禁じます
お問い合わせ
このページは、文化課が担当しています。
〒916-0024 鯖江市長泉寺町1丁目9番20号
文化振興グループ
TEL:0778-53-2257
FAX:0778-54-7123
文化財グループ
TEL:0778-51-5999
FAX:0778-54-7123