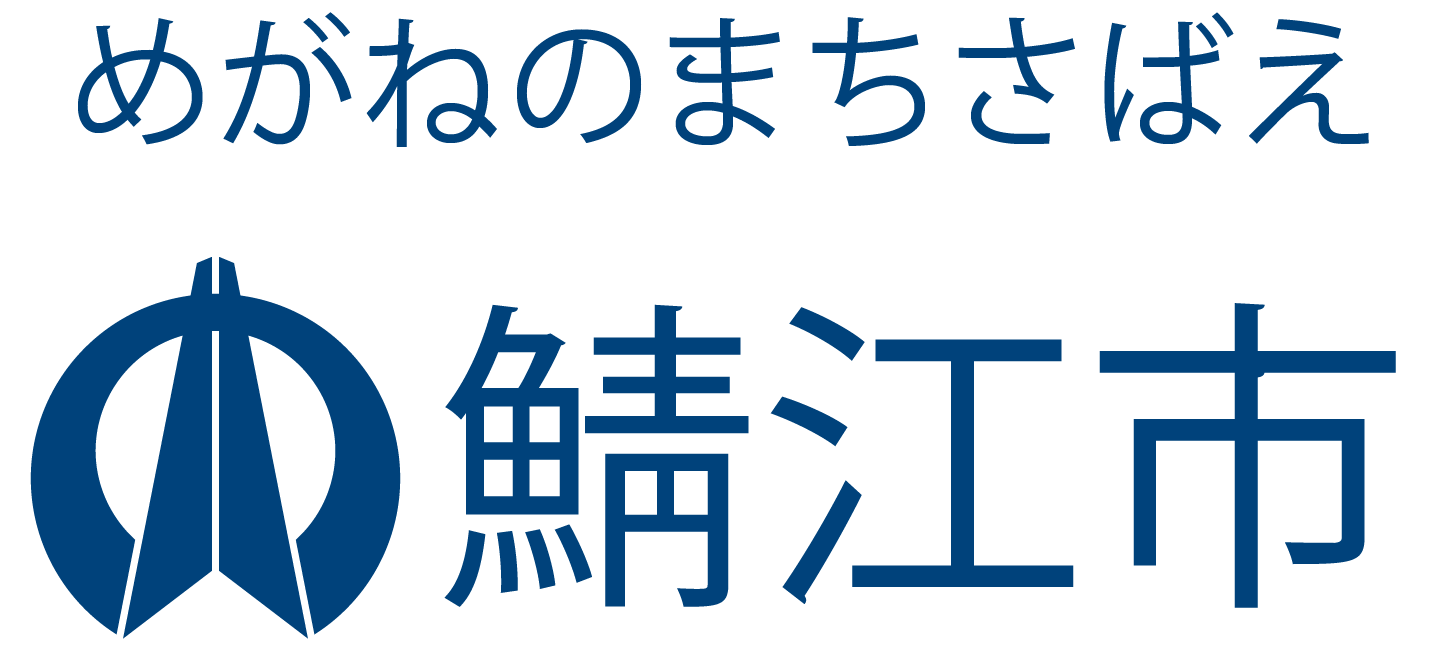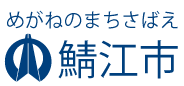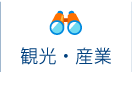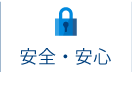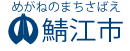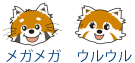国民年金保険料の免除制度・学生の納付特例制度
ページ番号:421-477-156
最終更新日:2025年4月1日
国民年金第1号の被保険者の方で、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
学生の方については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。
鯖江市役所の国保年金課または武生年金事務所の窓口で申請できます。(郵送による申請も可能ですので、事前にご相談ください。)
【すべての制度の手続きに共通して必要なもの】
・申請者本人の年金手帳(基礎年金番号通知書)
・申請者本人のマイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカード、通知カード等
・窓口に来られる方の本人確認書類
1点の確認でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
2点の確認が必要なもの:年金手帳、資格確認書、学生証等
・委任状
申請者本人以外が手続きをする時は、「委任状」も必要となります。
マイナンバーが確認できる書類がなければ、基礎年金番号を記載して申請することも可能です。
多段階免除の世帯構成別の所得基準の目安
平成18年7月分の保険料から、保険料の多段階免除制度が始まっています。
| 世帯構成 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4人世帯 (ご夫婦、お子さん2人)(注釈) |
172万円 | 202万円 | 242万円 | 282万円 | |||||
| 2人世帯 (ご夫婦のみ)(注釈) |
102万円 | 126万円 | 166万円 | 206万円 | |||||
| 単身世帯 | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
注釈:いずれも配偶者・子を扶養している場合
令和6年度以降の目安となる金額です。
免除の種類・届出方法・届出時期
| 免除の種類 | こんな場合 | 届出方法 | 届出時期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請免除 | 所得が少なく納付が困難な場合、失業や事業の休止または廃止、災害にあった場合など | 申請書を国民年金担当に提出してください。年金事務所による所得などの審査の結果、承認されれば、その期間の保険料は免除になります。 | 申請は前年の所得を確認する必要があるので毎年度必要です。(毎年7月が更新月になります。)ただし、継続申請をしている方は申請不要です。(注釈) | ||||
| 法定免除 | ○生活保護法による生活扶助を受けている人。 ○障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級、2級)を受けている人 |
届出により免除になります。 | 一度届出すればその事実が終了するまで免除になります。 |
注釈:平成17年7月から、全額免除または納付猶予が承認された方が対象です。
- 免除を受けた期間は、年金を受けるために必要な10年の資格期間に含まれます。ただし、一部免除については、納付すべき保険料が未納の場合は含まれません。
- 免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、免除を受けたときから2年が過ぎると加算額がつきます。(保険料の追納-参照)
- 免除期間中(一部免除については、納付すべき保険料を納付していること)の不慮の事故や病気で障害が残ってしまった場合は、障害基礎年金の支給対象となります。
納付猶予制度
所得が少ない50歳未満の方(学生を除く)が、将来の無年金・低年金となることを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により、保険料を猶予します。
- 被保険者本人及び配偶者が全額免除と同様の所得要件に該当することが必要となります。(世帯主の所得は判断の対象外となります。)
- 猶予を受けた期間は年金を受けるために必要な10年の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
- 猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、猶予を受けたときから2年が過ぎると加算額がつきます。(保険料の追納-参照)
- 猶予期間中に不慮の事故や病気で障害が残ってしまった場合は、障害基礎年金の支給対象となります。
- 納付猶予の所得要件を満たしたことにより承認された方は、継続申請の申し出をすることで、次年度の申請は不要となります。
![]() 保険料免除・納付猶予制度について 日本年金機構ホームページへのリンク(外部サイト)
保険料免除・納付猶予制度について 日本年金機構ホームページへのリンク(外部サイト)
学生納付特例制度
学生の場合は、申請をすることにより保険料の納付をする必要がなくなります。
(ただし、学生本人に一定額以上の所得がある場合を除きます)
| 区分 | 対象になる場合 | 対象にならない場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 学校等 | 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校 |
・海外の学校に留学の場合(一部対象校あり) |
||
| 所得の目安 | 学生本人の前年所得が128万円+((扶養親族の数)×38万円) | 左の金額を超える場合 | ||
| その他 | 申請の際は、在学証明書(または学生証の写し)が必要です。 | |||
- 納付特例を受けた期間は、年金を受け取るために必要な10年の資格期間に算入されますが、年金額には反映しません。
- 納付特例を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、特例を受けたときから2年が過ぎると加算がつきます。(保険料の追納-参照)
- 納付特例期間中の不慮の事故や病気で障害が残ってしまった場合は、障害基礎年金の支給対象となります。
![]() 学生納付特例制度について 日本年金機構ホームページへのリンク(外部サイト)
学生納付特例制度について 日本年金機構ホームページへのリンク(外部サイト)
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152