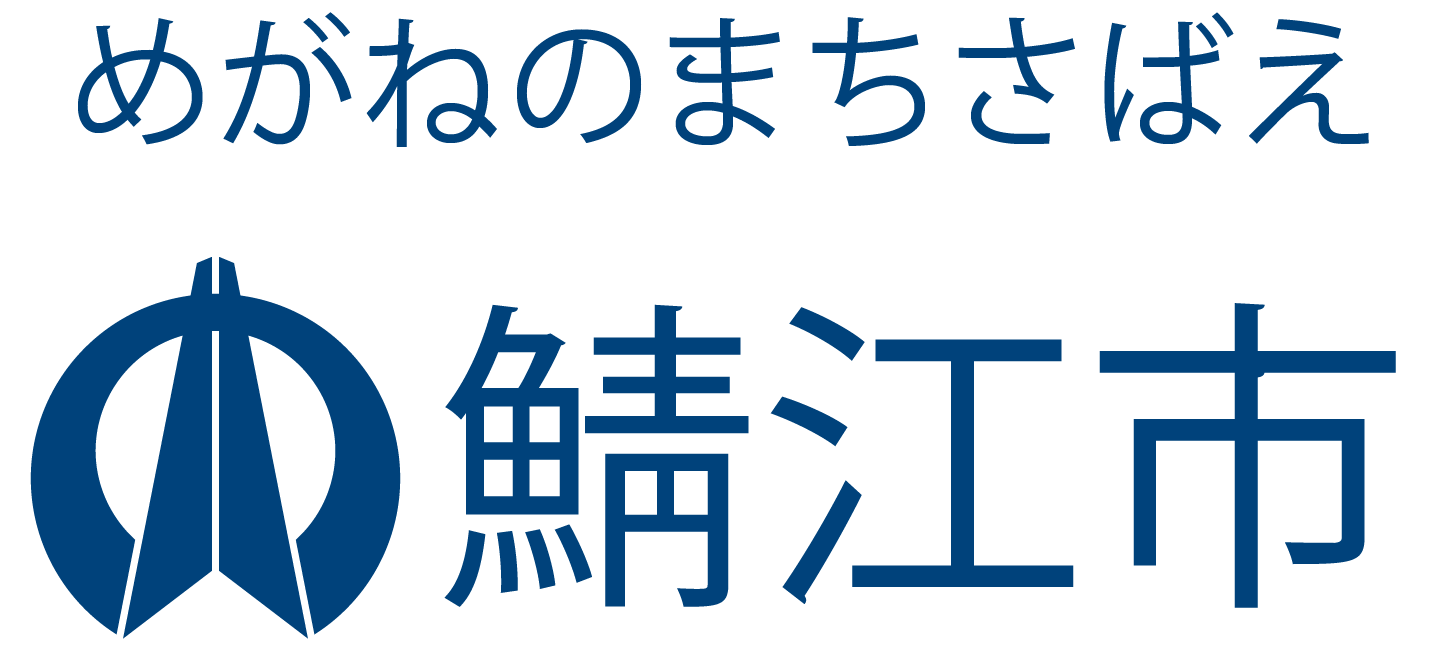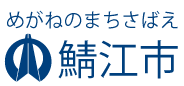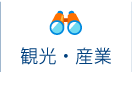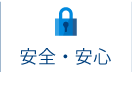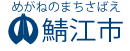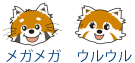夏季の食中毒に注意しましょう
ページ番号:888-804-099
最終更新日:2022年6月23日
夏季は、例年、腸管出血性大腸菌やカンピロバクターなどの細菌による食中毒が多く発生しております。また、高温多湿の条件下では細菌が増えやすく、食中毒のリスクが高まりますので、食中毒予防の3原則の徹底を心がけましょう。
食中毒予防の3原則
1 清潔(細菌をつけない)
食品にはいろいろな細菌が付いています。
それらの細菌を他の食品に付けないためには、まず、原材料は区分して専用容器に保管することが必要です。
さらに、加熱調理した食品や生で食べる食品は原材料からの細菌汚染を防ぐため調理器具を使い分けるなどの工夫が必要になります。
また、手指にも多数の細菌が付いているため、調理の際の手洗いは、食品に細菌を付着させないための第一歩として大切です。
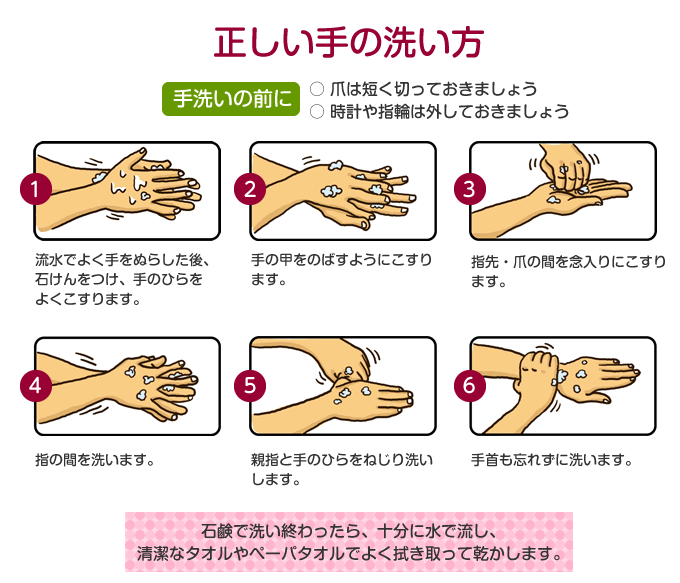
2 迅速または冷却(細菌を増やさない)
食中毒細菌の中には、カンピロバクターのように少量の菌で発病する細菌もありますが、多くは黄色ブドウ球菌、ウェルシュ菌などのように食品中で大量に増殖して食中毒を引き起こします。
そこで、食中毒を防ぐには、この「増やさない」ことが重要なポイントになります。
細菌には、それぞれ生育に適した温度帯があり、食品を保存する際には、この温度帯を避けた温度(冷蔵庫は10℃以下に、冷凍庫は―15℃以下)で保存する必要があります。
また、細菌は条件(温度・水分・栄養)さえよければ「ねずみ算式」に分裂して増えるので、食品を室温で長期間放置しないように心がけなければなりません。
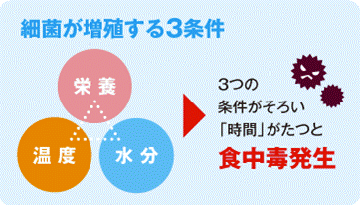
3 加熱(細菌をやっつける)
食品の十分な加熱がもっとも効果的な方法ですが、これが不十分で食中毒細菌が生き残り、食中毒が発生する事例が多いので注意しましょう。
一般的に食中毒を起こす細菌は熱に弱く、細菌が付いていても加熱(75℃1分以上)すれば死んでしまいます。
また、冬場に発生が多いとされるノロウイルスに対しては加熱が最も効果的な殺菌方法であり、85℃で90秒以上の加熱が必要です。特に二枚貝の生食はできるだけ避け、中心部まで十分加熱しましょう。
そのほか食器・ふきんを煮沸したり、次亜塩素酸ナトリウム溶液につけたりすること、手指を逆性石鹸などで洗うことなどによる殺菌、消毒も食中毒予防に効果的です。
ただし、黄色ブドウ球菌のように毒素を作る細菌は、ひとたび食品中で増殖すると、たとえ加熱殺菌しても、作られた毒素で食中毒が起こることもありますので、注意が必要です。

腸管出血性大腸菌・カンピロバクター食中毒を予防するために
夏のレジャーなどで、お肉を口にする機会が多くなる時期となります。一方で高温多湿のこの時期は食中毒の原因となる細菌が増えやすく、1年で1番食中毒が発生しやすいときと言われていますので、注意が必要です。
1 食肉は生や加熱不足で食べると、食中毒になる危険性があります
「腸管出血性大腸菌」や「カンピロバクター」は、家畜の腸にいる細菌なので、食肉に処理する工程で肉への付着を完全に防ぐことは困難です。このため細菌が付着した肉を生で食べたり、加熱が不十分な肉料理を食べたりすると食中毒になる危険性があります。
また、子どもは大人に比べて重症化しやすいため、さらに注意が必要です。

2 食肉は中心まで十分に加熱する 加熱前と加熱後のものをきちんと区別する
「腸管出血性大腸菌」や「カンピロバクター」は熱に弱いため、これらによる食中毒を防ぐには、中心部まで十分に加熱することが必要です。目安は、肉の中心部の温度が75℃で1分間以上の加熱が必要です。
また、十分加熱した後であっても菌から汚染を防ぐことが重要ですので、肉を焼くときに専用の箸やトングを用意して、自分が食べるための箸と区別しましょう。
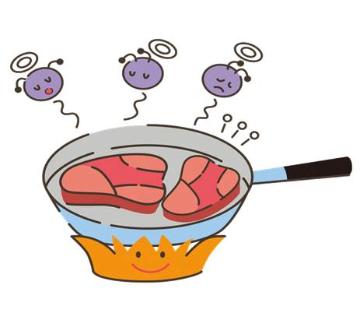
関連リンク
(厚生労働省ホームページ)
食中毒![]() 外部リンク(外部サイト)を設定します。
外部リンク(外部サイト)を設定します。
お問い合わせ
このページは、健康づくり課が担当しています。
〒916-0022 鯖江市水落町2丁目30番1号(アイアイ鯖江内)
健康増進グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116
母子保健グループ
TEL:0778-52-1138
FAX:0778-52-1116